晩年の時代
四十二、一日中の暮し
ファラデーの一生は冒険もなく変化もない。年と共に発見もふえれば、名声も高くなるばかりであった。
ファラデーの人となりは極めて単純である。しかしファラデーその人を描き出そうとすると、中々容易でない。種々の方面から眺めて、これを一つにまとめて、始めてファラデーなるものの大概がわかるであろう。
ファラデーの一日のくらしを記すと、八時間眠て、起きるのが午前八時で、朝食をとりてから王立協会内を一とまわりして、ちゃんと整頓しているかを見、それから実験室に降りて行って、穴のたくさんある白いエプロンをつけて、器械の内で働き出す。兵隊上りのアンデルソンという男が侍して、何でも言いつけられた通り(それ以上もしなければ、それ以下もしない)用をする。考えておった事が頭に浮ぶに従って、針金の形を変えたり、磁石をならべたり、電池を取りかえたりする。それで、思い通りの結果が出て来ると、顔に得意の色を浮べる。もし疑わしくなると、額(ひたい)が曇って来る。考えた事の不充分のために、うまく行かないからで、また新しい工夫をしなければならない。
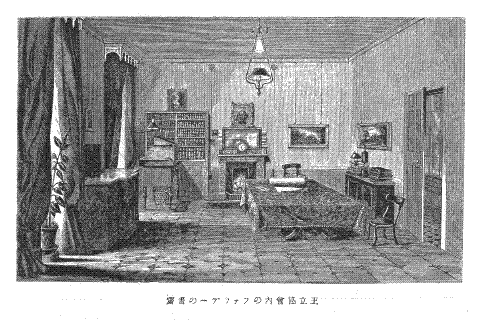
姪のライド嬢は実験室の隅で、針仕事をしながら、鼠(ねずみ)のように静かにしている。ファラデーは時々うなずいたり、言葉をかけたりする。時によると、ポタシウムの切れを水に浮べてやったり、あるいはこれを焔に入れて紫の光を出して、見せてやったりする。
もし外国の学者でも来て名刺を通ずると、ファラデーは実験を中止し、今まで出た結果をちょっと石盤に書きつけて、階上に来り、親切にいろいろの物を見せる。帰ると、再び実験に取りかかる。
午後二時半に昼食をし、それから書斎にはいる。室には、質朴な家具があり、窓の所にゴムの植木がある。ここで手紙を書いたりする。学会でもある日だと、出かける。帰ると、また実験室に行き、夕方にはやめて階上に来て細君や姪と賭(か)け事をしたり、謎をかけ合ったり、もしくはシェクスピアかマコーレーを声高に読む。その中に夕食になる。家族が集まっているので、朝出来なかった礼拝をする。これで、一日が暮れるのである。
夏の夕方には、細君や姪をつれて散歩に出かける。よく動物園に行った。新しく来た動物を見たり、猿がいろいろないたずらをするのを見て喜び、果ては涙ぐむことさえもある。
また金曜日の夕方だと、王立協会の書斎と講堂に行って、万事整頓しているかを見、その夜の講師に挨拶し、友人が来ると、「よくお出で」と言い、講堂では前列の椅子に腰掛け、講師の右手の所に陣取る。講演を聞きながら、時々前にかがみ、講演がすむと、周囲の人々に「ありがとう」とか、「おやすみ」とか言いつつ、細君と一緒に階段を上って自分の部屋に帰る。時には二三の友人と夕食をとる。
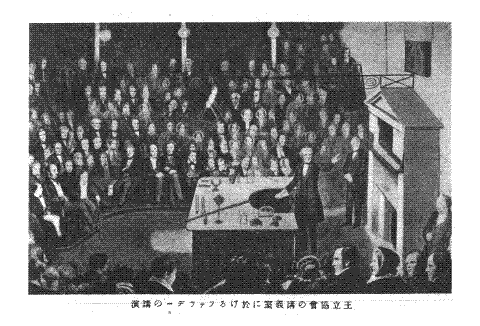
またファラデー自身が講師だとする。題目は前々から注意して撰み置き、講義の大体は大判洋紙に書き、実験図も入れて、番号まで附けておく。朝の中に覚えよいような順に器械を列べて置く。夕方になると、聴衆はどんどんと来て、満員になる。遅く来た人達は階段の所に腰を掛けたり、大向うの桟敷の後方にまでも立つ。その中にファラデーは、は入って来て、馬蹄形の机の真中に立ち、聴衆がまたと忘れられないような面白い話を始める。
クリスマス前に、小供に講話をする事もある。前の数列は小供で一杯。その後にはファラデーの友人や学者が来る。その中にサー・ジェームス・サウスも来る。聾であるが、小供の嬉しがる顔が見たいからといって来る。ファラデーは鉄瓶とか、ロウソクとかいうような小供の知っている物の話をし、前に考えもつかなかったような面白いことを述べて、それから終りには何か有益(ため)になる話をする。
また日曜日には、家族と一緒にレッド・クロッス町のパウル・アレイにある小さい教会に行く。この教会は地下鉄道の停車場が出来たので、今日は無い。午前の説教や何かが済んでから、信者が皆一堂に集って食事をし、午後の礼拝をすまして帰るのは五時半で、それからは机で何か書きものでもして、早く床につく。ファラデー自身が説教をしたこともある。
四十三、病気
一八三九年の終り頃からファラデーの健康は衰えて来て、初めには物忘れがひどくなり、その後は時々眩暈(めまい)を感ずるようになった。翌年には、医師の勧めで研究をやめた。けれども講演だけは時々していた。これもその翌年からはやめて、全く静養することにした。暇に、紙細工をしたり、曲馬、軽業、芝居、または動物園などに行った。細君はもはや王立協会には住めなくなって、動物園の近い所にでも移転しなければならないかと心配した程であった。
それからスイスへも旅行した。細君とその兄のジョージ・バーナードか、さなくば姪のライド嬢が一緒に行った。しかし細君の熱心な介抱により段々と良くなり、一八四四年には旧(もと)の体になって、また研究にとりかかった。
スイスへ旅行した折りには、ワルメールという所で、田舎家を借りていたこともある。窓からはチェリーの木の上に鳥の巣が見える。母鳥が雛にはぐくむのも見える。小羊が母を探して、戸の外までやって来る。ファラデーは日の昇るのを見るのが好きなので、姪に起してくれといい、姪はペイウェルベイの上が明るうなると、下の室へ降りて行き、戸を叩いて起した。ファラデーは入り日を見るのも好きで、野の草花の咲き乱れた山の上に長い夏の太陽の光が薄れ行き、夕ぐれになるとアッパーデールからの寺の鐘が聞えて来る。あたりが全く暗くなる頃までも眺めていた。
バイロンのチャイルド・ハロルドにあるレーマン湖のくだりや、またカレッヂの「モン・ブランの讃美」を読むのも好んだ。読んで感ずると、声にも現われ眼にも涙を出すという風であった。
入力:松本吉彦、松本庄八 校正:小林繁雄
このファイルは、青空文庫さんで作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
